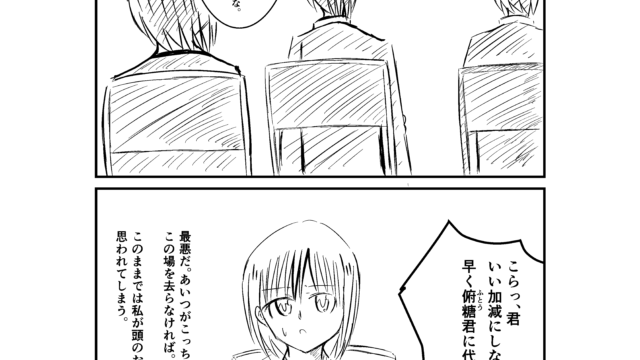オリジナル小説 エンジェルゲート第2章ー16

「輝希が生まれて口にした言葉がね、ぷっ、これが可笑しくて、なぜか“ちくわ〜”って急に喋りだしたらしいよ」
「むう……やはり増田は練り物と何かしら関係が」
と、お前がなんでそんな事知ってるんだよ、とツッコミを入れたくなるような情報まで出ます始末。レミは蛍の右隣で妙に納得したような顔をして頷いている。だが、だからと言って僕と練り物は何ら関係はない。
「ふう、まいいや。ほっとこ」
もう自由に話させておけばいいだろう。その内飽きるだろうし。輝希は椅子にかけ直し箸を手に取る。壁掛け時計は18時30分を指しており空腹を抑えるのもそろそろ辛かった。ましてや蛍の手料理の前ではなおさらだ。
「いただきます」
さてどれからいただこうか。エビマヨ、ハンバーグ、麻婆茄子、豚の生姜焼き、海藻サラダ、話に飽きて無心でおかずを貪るミカ、輝希はズラリと並んだおかず、と獣と化した女の子を眺める。
そういえば蛍の得意料理って僕の好物が多いな。そして、ふとそんな事を思った。
まあガサツな所もある彼女が輝希の好物を覚えているのかは分からない。むしろ知っていたら嫌いな物を作ってからかって来そうだな。なんて思い彼は苦笑した。
そんな事を考えながら輝希は一番手前の皿へと菜箸を伸ばす。彼の大好物であるエビマヨが盛られているお皿だ。一つ摘んでごはんの上へと持っていく、挟んだだけでも分かる衣の柔らかさだった、さて、味の方は、
ガチャクチャクチャ。モグモグ。
……パク。
うん。美味い。ふんわりとした衣に包まれた肉厚のエビ。それにうまく絡むほどよく濃厚なエビマヨソース。食べ慣れてはいるのだがやはり何回でも感心してしまう、自然と箸が進む味だった。
ガチャクチャクチャ。モグモグ。
パク。
「ねえ、」
輝希は堪らず不快な顔をして声を上げる。ちなみに先程から聞こえるガチャクチャクチャ。モグモグ。という音は別に輝希が出しているわけではない。その後のパク。という音が輝希のもの。
「ふぁい?」
顔を上げたのはミカ、他の二人はまだ何か話し込んでいるようだった。そしてその彼女達をよそに先程からミカはものすごい速度で料理を口に運んでいる。
「その、もう少し行儀よくできないかな? 音もうるさいし、顔とかタレまみれだよ」
輝希は苦笑いを浮かべながら顔を上げたミカを見る。その口元にはどの料理のか解らない程タレが付着しており、勢いよく食べるため指等にも飛散している。ちなみに彼女は菜箸は一切使わず自分の箸だけで皿に盛られている料理を取っている、そのため各料理には所々タレが混じり色が変わっている箇所があった。別にそれ自体はいいのだが、彼女達がいた世界にはそんいう文化はなかったのだろうか、それとも彼女が面倒くさがりなのだろうか、そこがなんとなく気になった。
「増田さん。うるさいです。喋らないで下さい」
何か勘に触ったのだろうか。普段よりも冷たくレミの様に輝希をあしらうミカ。隣に置かれた箱ティッシュから数枚を取り出して口元と指を拭く。そして湯のみの緑茶を啜り、
「そうやって私からごちそう(カロリー)をとろうという作戦でしょう。そうはいきませんよ」
ぷいっと顔を背けて再びミャグモグ。クチャクチャ。その目はさながら獲物を横取りされそうになった野生の獣だった。正直その執着に輝希は若干ひいた。
「いや、とらないしさゆっくり食べなよ。ってかごちそうのルビがカロリーってどんだけ飢えてるのさ」
苦笑いで手を横に振る輝希。自分に敵意はない事をアピールするため話しかけたのだが、今のミカにはそれすら気に入らないらしく、
「チッ」
「痛っ!!」
舌打ち、そしてエビマヨに入っていたグリーンピースが額にヒット。行儀の欠片もないその攻撃に額を抑えてうずくまる輝希。その額はまるでパチンコで打たれたかのように鈍くズキズキと痛み、とても女の子が軽く投げた時のものとは思えなかった。
「やめろミカ。食べ物を粗末にするなよ」
その様子を見かねてか、レミは腕組みをしながらミカを叱責する。そして同情するような顔で、
「そりゃ増田の家、もとい増田の料理が貧相で毎日ひもじい思いをしていたのは分かるぞ」
まさかの不意打ち。止めに入ったからといって別に輝希の味方ではないようだ。
「だが久しぶりのごちそうで興奮しているとは言え料理を無駄にしてはいけないぞ。そんな事をしたら料理を作ってくれた人、蛍に失礼だろ」
「はっ!」
その言葉で我に帰るミカ。その目はいつものパチクリとした大きな瞳。先程の野獣みたいな鋭さはない。