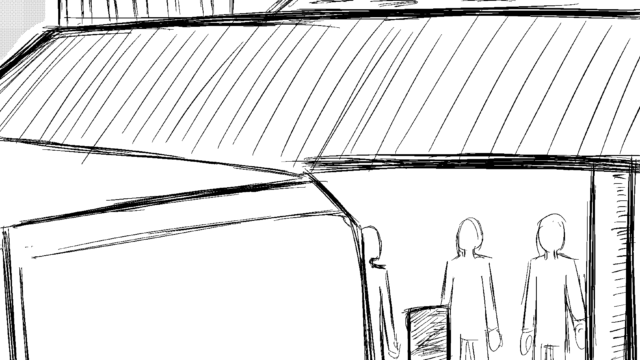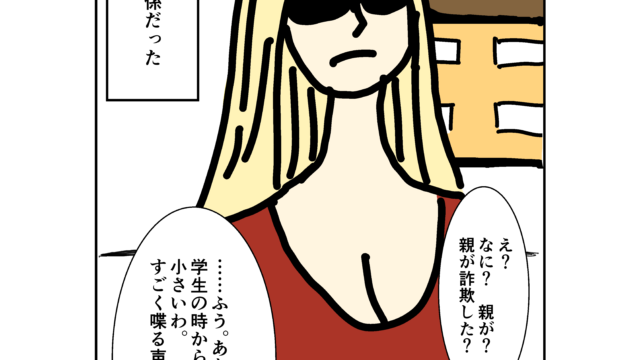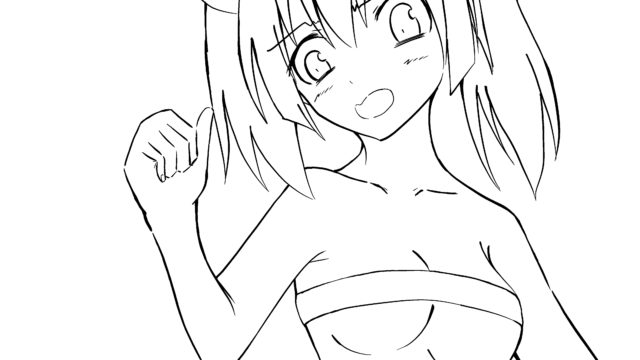オリジナル小説 エンジェルゲート第2章ー12

レミとミカとこれから一生を共にする。僕はそのことにやはり罪悪感を覚えていたのだろう。そんな僕の深層意識をよんだかの様に脳は夢を見せるのだ。
それは本当に幼かった頃の思い出。
でもどこまで遡っても、僕の隣には常に彼女がいた。そう、どの記憶でも何を思い出しても、彼の側には彼女の姿があって。
「てるちゃん、アタシきいちゃったよ〜」
それは確か小学校四年生の時だったろうか。その時から今程ではないにしても母親は仕事 で家を空ける事が少なくはなくて、輝希が小さかった事もあり、彼は当時よく赤土家にお邪魔する事が多かった。その日は朝出る時に自宅の鍵を閉めて、学校終わりにそのまま彼女の家にお邪魔していた。そして彼女、蛍はリビングでゲームをしながらそんな事を言ったのだった。
「えっ、聞いたって、なにを?」
時計の短針は三時を示していた。この時、蛍の母親は出かけており室内には床に座りTVゲームに興じる二人のみだった。ちなみに蛍の家はごく庶民的な二階建ての一軒家で、リビングもそれに見合った普通の造り。赤土家が全員揃えば少し窮屈に感じてしまうぐらいの大きさだった。だが輝希は自分の家の無駄に広いリビングよりも、このぐらいのスペースの方がどこか温かみを感じられて好きだった。
「えへへ、あのねー」
内心焦る輝希に対して、少しからかう様な笑顔を見せる蛍。聞いた話、輝希はその蛍が喜ぶ様な話に心当たりがあった。そしてどうやらそれは的中したらしく、
「輝ちゃん、二組のゆりちゃんに告白されたんだって〜?」
ニヤニヤしながらそんな事を言った。ゆりちゃん、本名は林ゆり子、ポニーテルの似合う背の低い女の子、二組ではかなり人気のある女子、そんな彼女から輝希は先日愛の告白を受けたのだ。当時幼いこともあって輝希は女の子と見間違うような顔立ちをしており、こういった事は珍しくなかった。しかし、輝希は贅沢な悩みかも知れないがそれをあまり好ましく思っておらず、蛍の耳に入らないように誰にも言わないようにしていたのだが……、
「……誰から聞いたの?」
「やまと君から」
やっぱりか。輝希はクラス一のお調子者の顔を頭に思い浮かべる。彼は面白い話題をどこかから仕入れてきては言いふらすのだ。きっとゆり子の方が輝希に告白した事を誰かに言ってしまい、それがあの噂好きに伝わったのだろう。と輝希は推測する。別に悪い奴ではないのだが、彼のせいで面倒な事になってしまったのは間違いなかった。
「で、どうするの、付き合うの?」
ワクワクとした少年の様な顔で期待している蛍。だが輝希はその顔を見て不機嫌に目を逸らす。だってこんな反応をするという事は、彼女は輝希の事など眼中にないという意味なのだから。
「……付き合わないよ」
少しは妬いてくれてもいいのに。そう考えていたせいか、ぶっきらぼうな言い方になってしまった。しかし蛍は特に気にした様子はない。彼女はゲーム画面を見つめながら、
「え〜、どうして、可愛いのに、輝ちゃんにはもったいないぐらいに」
確かにゆりちゃんは可愛かった。二組の男子が注目するのも分かる。告白の時も直接一人で来て、ありのままの気持ちを伝えてくれた彼女には好印象を持てた。だがそれよりも彼が気になっているのは、
「……だって、僕好きな子がいるから……」
「え? 何それ初耳っ! だれだれっ?」
再び彼女は目をキラキラさせた。ゲームのコントローラーを投げるように置いて、目の前に大好物を置かれた子供の様にグっと輝希に顔を近付ける。こんな事を言う前だからなのだろう。いつもは直視できる彼女の顔が恥ずかしくて見れない。だがここまで来たら言うしかない。彼は照れながらもボソッとした声で、でも彼女をしったりと見つめて言うのだ。