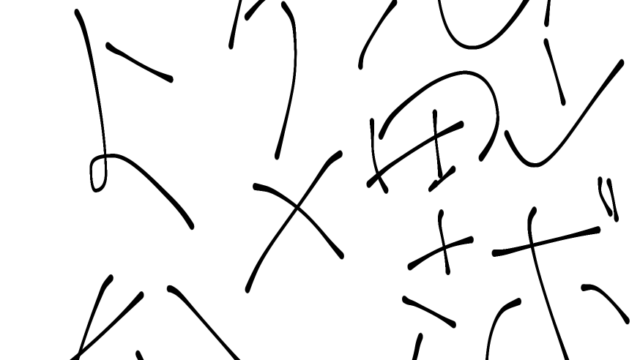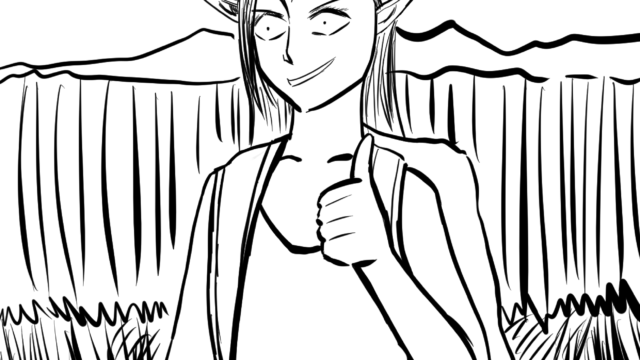オリジナル小説 エンジェルゲート第1章ー19

それはそうだろう。僕に髪が薄桃色だったり、地肌が小麦色の褐色している親戚なんていない。あっさりバレると思ったがそうでもないのか。さすがにずっと一緒にいて何でも知っている蛍に親戚ネタなど無理がある気は感じていたが、今は先程のように本気で疑っている様子はない。ただカマをかけて遊んでいただけなんだろうか。蛍は子供が好きな子に意地悪するみたいニヤっとした表情をして輝希を見る。
「ま、普通こんな可愛い子じゃ輝になびくはずないもんね〜」
「一言余計だって」
と蛍は全くもって平常運行だ。
「で、輝達は何してんの? 今日バスでしょ? とっくに帰ってると思った」
「少し東町に用があってね。てかそれを言うなら蛍だって。今日は部活なかったの?」
蛍は女子バスケ部のエースだった。まあ彼女は見た目通りに運動だったらなんでも出来るので体育の時はスター的存在だった。逆に僕はあまり運動が得意ではない。
「あははー、なんか最近身体の調子が悪くてね。今日は休んじった」
「え? 大丈夫?」
彼女は元気な声で言うがそれは珍しい事態だった。蛍は運動が得意以前に身体を動かす事が大好きなのだ。だから彼女が部活を休むなんてよっぽどの事だった。輝希は思わず彼女に一歩近づくが、
「ちょ〜、触ろうとしないでよ変態〜」
戯けながら後ずさる蛍。別に触る気などないのは蛍もわかっているはずなのに、なんだか反応が大げさだった。
「いや、別に触ろうとしたわけじゃ」
「したよ〜、目がやらしかったもん」
なんだかとてもいい雰囲気を醸し出す二人。歩道に隣接する店先のベンチでそんなラブコメなやりとりをするもんだからすれ違う人達は、『ちくしょう』といった殺意を醸し出していたが二人は気付かない。するとそれを見守るこちらの二人は、
「おい、ミカ。こういう時私は何をすれば良いと思う?」
「クレープ食べます? レミちゃん」
「いや私バナナ駄目だから」
温度差が半端なかった。まるで恋愛ゲームの真ヒロインにより座を取られたサブヒロインそのものだった。そんな空気を見かねたのか、
「ちょっと二人とも。私ともお話してよ。ってか何て名前なの?」
先程とは違いフレンドリーに歩み寄る蛍。二人は彼女の意外にも好意的な態度に拍子抜けしながら、
「あ、申し遅れた蛍、私増田の親戚一号のレミです」
「同じく親戚二号の、うっぷ、ミカです」
そろそろその反応はやめてくれ。本当の親戚だったらどうするんだよ。知人に紹介するたびに催す親戚なんて僕はいやだぞ。と思いつつも彼はやっぱりミカが心配で、
「おい、大丈夫か、ミカ?」
「ええ、心配ご無用です。二号なので大丈夫でした。一号なら正直危なかったですね」
「何その基準!?」
じゃあこれからは10号とか遠い親戚と表現してもらおうと輝希は考える。その方が彼女のお腹にも優しいだろう。
「うんよろしく。私、輝の幼なじみを16年やっている赤土蛍。仲良くしよ、だってしばらく輝の家にいるんでしょ?」
「はい。全く持って不本意ではありますが」
「イエス。もしかしたら生涯添い遂げる形になるかも知れませんが」
「いやイエスじゃないよ。まあ長くなるかもしれないけど、問題が解決したらこの子達は帰るから」
ポンとレミを叩く輝希。あれ? でも僕が死ぬまでって事はそういう事になるのか。と軽く冷や汗が流れた。
「へえ」
蛍はレミとミカをしばらく見つめていた。その目線は輝希からは分からないが、およそ彼女のものとは思えない程どんよりとしたものだった。輝希がしっかりと見ていたのならば彼女の異常にも気付ただろう。その意味には気付けなくとも。
「で、輝はもう用事って済んだの?」
不意に顔をあげて輝希を向き直る蛍。やけに長い間二人を見ていたけどまだ疑われているのだろうか。
「え? ああもう終わったからそろそろ帰ろうかなと。」
ならばここには長居するべきではない。ひとまず帰って彼女の疑いが冷めるのを待つべきだろう。
「あ、私はこれから用事済ますんだ」
「そっか。じゃあ僕達はバスで帰るとするよ。こっからだと第二小学校が近いかな」
よかった。彼女とはひとまずここでさよならだ。それにもう蛍に彼女達の存在は知れてしまった。ならば誰に知られても怖くない。堂々とバスで帰ろう。先程の乗車中みたいに奇異の視線を浴びるのは嫌なので、下界状態の彼女達を連れて行こう。奇異ではなく羨望や嫉妬をいっぱい受けようじゃないか。彼はそう考える。