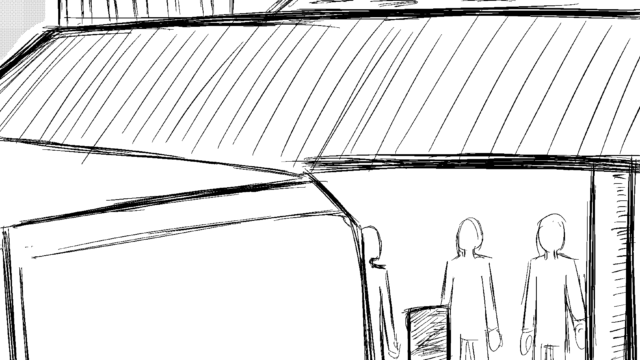オリジナル小説 エンジェルゲート第3章ー7

「あ、いやそうじゃなくて」
と隣を不安そうに振り返る輝希。するとそこには想像の斜め上を行く光景が。
「あ、あ、ま、増田さんのか、彼女、彼女? 私が? 嘘だろうが、おいおい」
「お、おちつけミカ、なんか口調が変だし」
「は、はい、そうですね、もう、私も大人だし、大人。こんな事一つで腹は立ててられませんよ」
スーハー。スーハー。深い呼吸を繰り返し鼓動を落ち着けていくミカ。徐々に青ざめていた顔は元の色を取り戻していく。おお、ミカがこんなに早く復帰を。輝希はミカの成長に少し胸熱くなるものを感じた。が、
「可愛らしい彼女さんですな。まるでタレントさんみたいですよ。羨ましいなー、はは」
「お、大人、お、おと、あ、あ、あばば、あばば」
間もなく追加の爆弾が投下された。と同時にミカからは謎の痙攣、成長したと言っても今の彼女ではまだこの言葉を受け止める事は出来ないようだ。しかもこの調子では第二、第三の投下も時間の問題だろう。輝希は慌てて、
「いや、違うんですよ、この娘は別に、」
「おや、そうなんですか? お似合いなのになー」
「いえいえ、こんな可愛い娘が僕の彼女だなんて滅相もない。もったいないですよー」
顔は笑顔を浮かべているが輝希の心にそんな余裕はない。引き攣った笑みのままチラチラとミカの様子を見るが、もう彼女の顔からは血の気が完全にひいている。その一切の余裕のない虚ろな目は限界を感じさせた。だがこの小島という男、見た目からも分かる通りあまり空気の読めるタイプではないのだろう。輝希の心配やミカの変化にも全く気付かずに、
「ははは、そんな恥ずかしがらなくとも、みてればわかりますよ」
「ぷつん」
ああ。わかりましたとも。
今、ミカの頭にある何か線的な物が音を立てて切れたのがね。
「さて、ではそちらのお嬢さん用にオススメなのはーー」
「せあぁっー!!」
「あべっふ!」
あべっふ。それがマサシ電気店員小島の最後の言葉となった。彼は頬にミカ渾身の右ストレートを喰らい宙を舞い、ってーー
「えええー! 何してんだミカー!」
まるで他人事のように男の最後を語っていた輝希、我に返って店員をぶん殴ったミカを振り返る。しかし荒い呼吸に殺人鬼のような鋭い眼光、そんな姿をした今の彼女にあれこれ言っても無駄だろう。とても冷静な状態とは思えない。というかそんなに嫌なの? 僕の彼女が。
「いやいや、どうするんだよ、この人」
とは言えこのままにしておくわけにもいかないだろう。仰向けになった店員を見下ろして輝希は言う。すると呼吸を整え終わったミカはニッコリとした笑顔を浮かべるのだ。でもそれは普段の無邪気なものとは違って、
「大丈夫です。増田さんはゆっくりイヤホンを選ぶといい。その間にこの男にはトドメを刺しますので」
「店員さんの命が懸かっている状態でゆっくり選べるか!」
「よろしい。ならこの男は瞬殺しましょう」
「だからって早めるな! ていうかトドメを刺そうとするな!」
グイッと胸ぐらを掴んで喉元にフィニッシュを決めようとするミカ。いかん、どうやら戻るどころか一つ向こう側の冷静さへ到達してしまったらしい。
「なら放っておきましょう。大丈夫、この男も電気屋店員のはしくれ。この程度なら日常茶飯事でしょう」
「いや、そんな危険な職業じゃないからね、電気屋って」
「まあ、とりあずここに寝かせておこう。気がついたらちゃんと謝らなくちゃ」
小島の上体を持ち上げて隅へと移動させて、柱にもたれかけさせ寝かせておく。周りの客は何があったか気付いていないようだし、店員も近くにはいない。なら事を大きくするよりはこの方がいいだろう。おそらく命に別状はないだろうし。……多分。
「さて……お、これ」
再び品定めをする輝希、無数に並ぶイヤホン達、その中でも一際気になる物があった。
「綺麗な形してるな。なんか大人っぽいっていうか」
イヤホンコーナー平台の目立つ位置に陳されていた高級な雰囲気のイヤホン。手に取ったのは大手メーカー、モミーのカナル型のイヤホンMMー10000プレミアムシリーズだ。どうやら今売り出し中の商品らしく特設コーナーが設けられていた。洗練されたデザインに音質にこだわりを感じる機能性、そしてイヤホンのユニット部分はどうやらアルミニウム製、プラスチックにはない高級感が感じられる。
「でも色が……お、あったあった」
手に取ったメタリックピンクを元に戻して後ろの方を探す輝希、その中から見つけたのはネイビーブラック。上品な色合いでより一層高級感が際立って感じられた。
「うん。彼女にピッタリだな」
レミの艶やかな黒の長髪によく映える大人びたイヤホンだ。これならレミも喜んでくれるだろう。