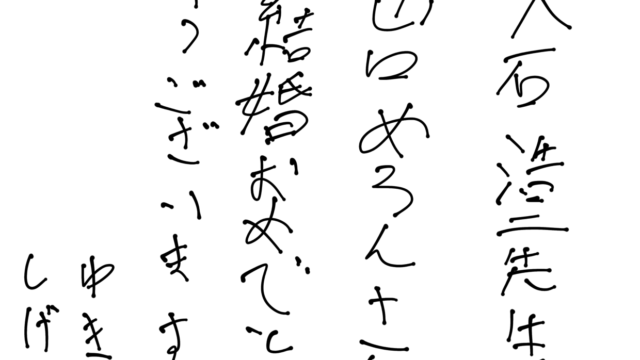オリジナル小説 エンジェルゲート第3章ー8

「よし、じゃあこれ買って来るよ、ミカ」
「あれ増田さんもう決まったんですか」
「ああ、レジに行って来るからさ、ミカはこの場で待っててくれないか」
当たり前のように自分も付いて行くつもりだった彼女はきょとんとした顔で、
「なんでです?」
「いやこの小島って人をこのまま置いておくわけにも行かないだろう。もしかしたら目を覚ますかもしれないし、だからその時は、」
「わかりました。その時は面倒な事にならぬようもう一度眠らせればいいんですね」
「だから意識奪おうとするなって!」
その言葉で思う。彼女一人をここに置いていくのは危険だと(小島さんの命が)。
というわけで輝希はミカを連れてレジへと向かい、商品を購入してプレゼント用の包装をしてもらった。ちなみにその後、店員を連れてイヤホン売り場に戻ると丁度小島さんは目を覚ましたところだった。しかしあまりの衝撃から何故こうなったのかを覚えていないらしく、自分で転んで気絶した事にしてその場は偶然丸く収まった。そして輝希達は小島さんに対する罪悪感を少し抱きながら店を後にした(多分ミカはそんな事思ってないだろう)。
「さて、増田さん」
一時間ぶりに店の外へと出た二人。輝希より足早に外へ出たミカは今日一番のスマイルでこう言うのだ。
「どこで食べましょうか?」
ドキッ、としてしまう笑顔。しかしその裏は溢れんばかりの食欲で溢れている。とは言えまだ腕時計で確認すれば時刻は11時00分、昼食には早い時間だ。ミカはいつでもたらふく食う準備万端のようだが輝希はそうでもない。ならばもう一つの用事を先に済ましておこうか。輝希はそう思ったが満面の笑みの彼女に、まだ食事が後回しになる事を伝えるのはなんとなく勇気が必要だった。彼は戸惑いながら少し申し訳なさそうに、
「ごめんミカ、実はもう一件寄りたい店があるんだけど」
頭を下げながら輝希はチラリとミカを見る、すると彼女は口を半開きにして面食らった表情をしていた。電気屋の時からこの食事だけを楽しみにしてきたミカの事だ、やはりショックだったのかもしれない。もしかしたら怒られるかも。そう覚悟したが、
「わかりました」
「え? いいの」
「あたりまえじゃないですか」
なんともすんなり承諾してくれたものだ。しかし輝希には違和感が残るミカの対応、というか逆に喜んでいるようにも見えるんだけど。戸惑う輝希にミカは笑顔のまま、
「もう一件と言わず何件でも付き合いますよ、ハンバーグですか? ステーキですか」
もちろんだが別に飲食店にもう一件寄ろうという訳ではない。言葉の脈略から大体の人はわかりそうなものだが。輝希は手を左右に振りながらその誤解を解く、と同時に今度こそミカの機嫌を損ねる事を覚悟する。
「いやそう言う意味じゃないよ、アクセサリー屋なんだけどさ」
「アクセサリー? 知らない食べ物ですね。こっちに来て大体の食物については勉強したつもりですが」
「食べもの以外についても勉強しなさい。えっとね、アクセサリーってのは装飾品の事だよ」
「装飾品、ああ、あれですね、お弁当によく付いているあの緑色の草、えと、バランーー」
「そんなものを腕とかにつけてたらバカみたいだよ」
どうやら本当に食べ物関係は勉強したんだろうな、おそらくレミに聞いてもバランという名詞は出てこないだろう。しかも、
「ちなみにあれは人工バランといって本物のバランではないんです。といってもバランという物もないんですけどね。あれは元々ハランという植物を真似たものであって、」
無駄に詳しい。
「いやわかったわかったよ、でも今から行く所は食べ物と何の関係もないんだ。わかるだろ?」
「そうですか……」
食べ物と何の関係もない。どうやらそれが決めてとなったようだ。行きたくない、と文句を言う事もなかったがミカはガックリと肩を落とした。
「ちなみにその装飾品とやら、それもレミちゃんへのプレゼントでしょうか? ……私にじゃなくて」
弱々しく呟くミカ。でもそれはどこか落ち込んでいるのとは違って見えた。
「え? どういう意味?」
もしかして焼きもちやいてる?
「いえ、ならレミちゃんだけ2つ貰えるという差別+もう一件寄らなければならないという拷問=で私は寿司を要求してもいいんじゃないか、と思いましたっ」
ではなく、ただ不公平を嘆いていただけらしい。言い分も子供みたいだな。と苦笑いが自然とこぼれた。