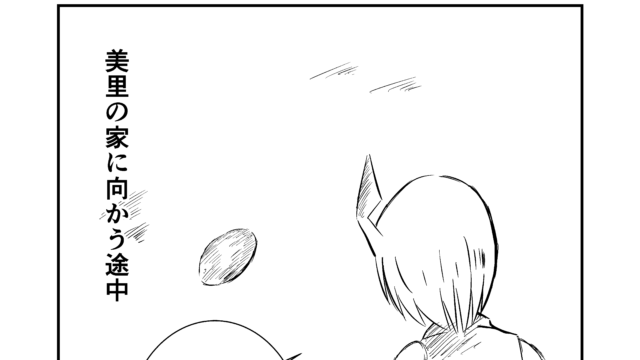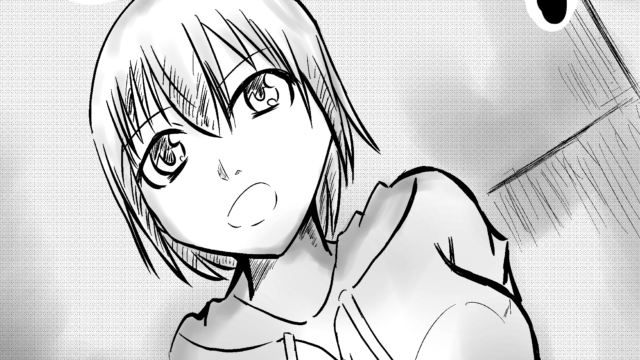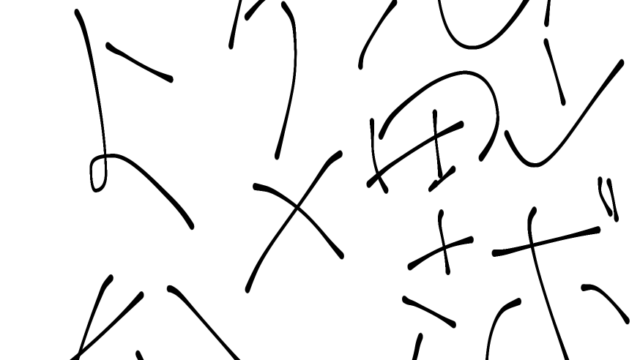オリジナル小説 エンジェルゲート第4章ー10

以前の彼からは想像もつかない事を述べるイワン。昔の彼は自分の価値観など語らない事務的な人間だった。ミカはそんな彼を訝しんだ視線で見つめる。
「おそらく、人間の記憶を食べたせいで記憶が混同しているのだろう。まあ耳を貸すな、ただの戯れ言さ。くだらない」
地獄の果実に手を出した、悪魔に成り下がった者にはよく見られる状態だった。彼等は全員いわば記憶の塊を口にしたのだ、溢れ出す知識や経験に歓喜する者、混じり合う記憶の中で自分は人間なんだと勘違いをする者、反応は様々だが、皆イワンのように“誰か”の一面が出てしまう事があった。
レミの侮蔑するような言葉にイワンは初めて不快そうな態度を露にした。
「君、いやレミ、その言い方は失礼だな。オレが彼女を物語のヒロインにしてあげたんだ。悲劇の、衝撃的な形で死を遂げる、僕が求めるヒロインにね」
「だまれ、イワン」
「それに俺は彼女の願いを叶えてやったんだ。蛍の望み通り少年の命を蘇らせた。それに、彼女にも短いながらも少年といられる時を与えてやったんだ……彼女もあの世で僕に感謝しているだろうね」
「……ふん、よく言うな。あんな継ぎ接ぎのような魂で復活させて、彼女がどれだけ苦しかったか」
正確に言えば先程まで蛍を動かしていたのは魂ではなかった。彼女の身体に結びついたのは魂に変わる核。それはイワンが強い感情から生み出した擬似的な魂。そしてその核は時が経てば経つ程に彼女の身体を蝕み続けていた。
「蛍の痛みがお前に分かるのか」
レミが特に苛立っている点、それは、イワンが意図的に蛍の身体を蝕まれていく仕組みにしたという事だ。イワンは優秀な男だった、彼程の力を持つものなら作る事も出来たはずだ、短時間しか持たないものであれば完璧な魂の代わりを。しかし彼はそれをしなかった。その理由はおそらく先程から述べている美的感覚によるものだろう。だが、だからと言って納得が出来る訳が無い。
「まあ、そう睨まないでくれ。僕だって望んで彼女をあんな身体にした訳じゃないんだ、言ったろ? 悪魔に成りかけていたせいで力が不安定だったんだ。本来なら彼女に普段と変わらない身体を与えてやれた……」
誤解を解こうとしたイワンはそこで口元を抑える、しかし指の隙間からは明らかに喜んでいると分かる表情が漏れていた。
「だが、痛みを必死に堪える彼女もまた良かったな。少年に気付かれぬよう無理にでも笑顔を見せる姿、痛々しくも、愛おしかったよ……まあ、とにかくなんだっていいだろ」
彼は宙を見上げ蛍を思い浮かべる、下界に降りてずっと行動を共にしていた少女、彼女は自分のせいで常に苦痛に苛まれていた。レミの言う通りそれは並大抵の痛みではなかったはずだ。
しかし、イワンであり遠藤来人もある彼は、心の底からこう思うのだ。
「役者は監督のコマなんだ。だから彼女をどう使おうが僕の自由なんだよ」
そう、それは彼の記憶に深く刻まれた価値観。来人にとって役者などは表現に必要な道具でしかない。そしてそれは蛍も例外ではないのだ。
「そうか……もう、喋らないでくれ。イワン」
「そうだな……お互いこれ以上話す事はないか」
「はい、悪魔になった以上、あなたはもう敵です……それに蛍さんのためにもあなたを倒します」
これ以上今のイワンに何を言っても無駄なのだろう、それどころかその気が触れた考えのせいでこちらの気分が悪くなっていく一方だった。ならばレミとミカのやる事は一つ、イワンの始末だけだ。
「そうだな、ではまずあと片付けを先にしなければ、な」
ぐっと横に伸ばした手をイワンは軽く閉じた、すると、
「あ……」
その光景に輝希は弱々しく一言声を漏らした。だがそんな情けない声が出るのも無理は無い。彼の目の前で砂、いや粒子のように蛍の死体は衣服を残し崩れていく。そしてその崩れた細かな欠片はまるで吸われるように天へと昇っていった。徐々に光の粒へと姿を変えていく蛍の身体。とても神秘的で普段なら見とれてしまうような光景。でも、
「蛍……」